1960年代の中ごろ、ニューヨークで新しい芸術の試みがなされようとしていた。
中心となった人物は Andy Warhol。50年代に広告業界のデザイナーとしてキャリアをスタートさせた Warhol は、50年代末からアーティストに転身し、「シルバー・ファクトリー」と名づけた自らの工房に出入りしていたバンド The Velvet Underground とともに、アルバム'The Velvet Underground & Nico'を世に送り出す。
僕が最初にこのアルバムを聴いた時に抱いた印象は、80年代のアメリカで生まれたオルタナティヴ・ロックそのものだ、というものだった。ひずんだギターの音、陰影の濃い内省的なボーカル…。しかし、The Velvet Underground はオルタナティヴ・ロックが生まれるずっと前の、The Beatles や The Beach Boys と同じ時代のバンドだった。
その音楽は、時代にとってあまりにも早すぎたのだろうか。彼らは商業的にほとんど成功することなく時代の幕の陰に消えていった。
今日は、Andy Warhol と The Velvet Underground のそれぞれの思惑を踏まえつつ、今なおロックの歴史に燦然と輝くこのアルバムについて書いてみたい。
と、なんだか小難しいことを書いたが、このアルバムは非常にキャッチーな作品であり、今なお聴く人を魅了する力がある。聴いたことのない人はぜひ一度聴いてみてほしい。その上で、この記事に書いてあることを踏まえてあれこれ想像してもらえると幸いだ。
このアルバム'The Velvet Underground & Nico'のメッセージを一言で言うと、人間は機械になれるのか、あるいはそれらは対立する存在なのか、ということだと思う。
「人間は機械だ」という立場をとったのがプロデューサーの Andy Warhol であり、「人間は機械ではない」という立場をとったのがパフォーマーの The Velvet Underground だ。
その対立の妙が、このアルバムにはある。そして、Warhol がこのアルバム以降バンドのプロデュースにかかわらなくなったのも、その対立のためだと思われる。
1960年ごろから、Warhol は芸術作品から個性を消し、「特別であること」「独創的であること」を否定し、物体のありのままの美しさを追求するようになる。それは、以下のような発言から読み取れる。
(発言と訳はすべて六本木森美術館で開催の「アンディ・ウォーホル 永遠の15分間」より引用)
"In the future everybody will be world famous for 15 minutes."(将来、誰でも15分間は世界的な有名人になれるだろう)
"Why do people think artists are special? It's just another job."(アーティストが特別だなんて、どうしてみんな思うんだろう。他の仕事と何も変わらないのに)
"Well, I used to work for these magazines and I always thought I was being original and then they'd never want it... This is when I decided not to be imaginative."(以前、雑誌の仕事をしていたことがあった。自分ではいつも独創的だと思っていたけど、そんなもの誰も相手にしてくれない。…その時から僕は、想像力を働かせたりするのはよそうと心に決めた)
彼は活動の幅を広げた後にも、このような発言をしている。
"But why should I be original? Why can't I be non-original?"(なぜオリジナルである必要があるのだろうか?人と同じじゃいけないのかい?)
"I started repeating the same image because I liked the way the repetition changed the same image."(僕は同じものを繰り返し描くようになった。繰り返し描くと、違ったものに変わっていく。その変わり方が好きだからだ)
彼は「機械になりたい」と発言し、同一のイメージを連続・反復させ、アシスタントを雇って大作やシリーズ作品を制作した。有名なマリリン・モンローをはじめとする著名人の似顔絵や、キャンベル・スープの缶に、その哲学は表れている。
The Velvet Underground の1stアルバム、'The Velvet Underground & Nico'も、そのような観点から読み解くのがよいだろう。
つまり、Warhol からすると、このアルバムは「人間には個性なんてない、ただの機械だ」というメッセージを込めたものだったと考えられる。
僕は「アンディ・ウォーホル 永遠の15分間」展で、このアルバムが出された頃にWarhol によって撮影されたバンドの練習風景の映像を観たが、それはバンドのボーカルの Nico が延々とタンバリンを叩いているのをさまざまな角度から映したものだった。これこそが、Warhol の込めた「永遠と同じことを繰り返す機械になりたい」というメッセージの象徴だと思う。
一方、The Velvet Underground の音楽には、人間の生々しい感情が詰まっている。
それは、Warhol の抜けた直後の2ndアルバムを聴いてみるとよくわかる(参照:'White Light/White Heat' - The Velvet Underground / きみは、この白い熱を感じるか。ロック史に残る傑作。
彼らは、ドラッグやセックス、狂気、そして死すらもその音楽のモチーフとし、グロテスクな人間の感情を描いているのだ。
1stアルバムにおいても、彼らが本当に描きたかったのは「人間の生々しさ」であったに違いない。
(余談ではあるが、のちにロックの世界にも大きな影響を及ぼす1970年結成のドイツのテクノグループ Kraftwerk は、「人間は機械である」というメッセージを掲げていた。もしも Andy Warhol があと10年間大衆音楽の世界にとどまっていたら、Kraftwerk と何らかの接触をしていたのではないだろうか。)
この「機械」と「人間」の対立が、'The Velvet Underground & Nico'の音楽には見事に反映されている。
その対立は、「誰がボーカルをとっているか」に象徴されている。
このアルバムには、メインボーカルは2人いる。1人はいわずとしれた Lou Reed。そしてもう1人が、Warhol が連れて来た女性ボーカルの Nico である。
当然、Reed がボーカルをとる際は「人間」が、Nico がボーカルをとる際は「機械」が、それぞれ強く表現されていると考えられる。
それでは、内容を見ていこう。
#1 Sunday Morning
#2 I'm Waiting For The Man
#3 Femme Fatale
#4 Venus In Furs
#5 Run Run Run
#6 All Tomorrow's Parties
#7 Heroin
#8 There She Goes Again
#9 I'll Be Your Mirror
#10 The Black Angel's Death Song
#11 European Son
アルバムは、印象的なチェレスタの音が優しく響く#1"Sunday Morning"から始まる。
Velvet Underground-"Sunday Morning" from ...
もともとは Nico が歌う予定だった曲だが、Lou Reed がどうしても歌いたいと譲らず、ボーカルは最終的に Reed がとっている。
つまり、もともとは「機械」側の曲だったのだ。それは、整然とした音作りや、基本から少しも外れないコード進行に表れている。
ただ、非常に美しい曲にもかかわらず「気を付けろ、世界はお前の後ろにある」(Watch out the world's behind you)などという被害妄想っぽい歌詞があるところを見ると、すでにドラッグに冒されているようにも感じる。そこにかぶさってくる Reed のボーカル。
言うなれば、淡水と海水の混ざる汽水域のような曲だ。
静かな曲に秘められた「機械」と「人間」の対立は、この後に続く本作の激しいアップダウンや、バンドの波乱に満ちた運命そのものまで、予言しているように感じる。
#2"I'm Waiting For The Man"は、その名の通り男を待っている曲である。
これもボーカルは Reed。荒々しいギターのストロークからもわかるように、この曲はかなり「人間」くさい。特に、「レキシントン125番」と歌うところのコードはI→III→IVでちょいと不思議な感じ。
この前も書いたけど、もともとロキノン系からロックの世界に入っていった僕がこのコードを聴いて思い出すのはSUPERCARのcream sodaのイントロのコード進行だ。あれはI→IM7→III→IVの繰り返しである。
そういったコードの面からも、「薬物が切れて早く売人から薬を手に入れたい男」を描いた歌詞の面からも、この曲が「人間くささ」を歌っていることは明白である。
なお、この曲は日本では男娼の歌と紹介されることが多いようだが、「手に26ドルを持っていること」に矛盾するので、僕は違うんじゃないかと思う。
では主人公が身体を売る方ではなく買う方なのではないか、というふうに考えるとどうだろう。その場合は、「あいつはいつも遅れてくるんだ」という、相手の方が立場が上であることをほのめかす描写の意味がわからなくなる。
「立場が上の男に金を払ってまでセックスしてもらう」ということはおそらくありえない(相手が加藤鷹かアダム徳永あたりならありえるのだろうか?)。なので、この曲は売春とはほとんど関係ないのではないか。
#3"Femme Fatale"で、ようやく Nico のメインボーカルが聴ける。タンバリンも、おそらく Nico が鳴らしているはずだ。
先に言っておくと、Nico がボーカルをとっているのは#3、#6、#9である。すべて3の倍数である、という規則性がまたしても「機械」を連想させるのは気のせいだろうか。もし#12があったら誰がボーカルをとっていたのだろうか…などと考えるのもおもしろい(アルバム自体はカオスな曲#11"European Son"で終わっている)。
彼女は、「男がやってくるのを待っている」#2と対比するように、いきなり"Here she comes"と歌う。
She's going to break your heart in two, it's true(彼女はあなたの心臓を2つに引き裂くわ、本当よ)
It's not hard to realize Just look into her false colored eyes(それはほとんど気付きもしない一撃で、あなたはただ彼女のカラーコンタクトを入れた目を見るだけ)
普通に恐い。このへんのグロテスクな情景描写は、2ndアルバムにもふんだんに見られるものだ。
グロテスクといえば、このアルバムの有名なバナナのジャケットには、「ゆっくり剥がして見ろ」(Peel Slowly and See)という記載があり、その通りにジャケットを剥がすとピンク色の果肉が現れる。
何の変哲もない日常に潜む狂気。それを、#3のような淡々とした音楽に込められたグロテスクな世界観で表現しているのが、この'The Velvet Underground & Nico'というアルバムなのだ。
#4"Venus In Furs"。
なんだかアジアンな香りのする重厚な音楽である。
しかし、歌詞を読むとそんな悠長なことを言っていられなくなる。「鞭」「ベルト」「歪んだ愛」などのキーワードからも推測されるように、この曲はSMの曲だ。
この曲は「マゾヒズム」の語源となったオーストリアの小説家マゾッホの作品"Venus In Furs"「毛皮を着たヴィーナス」を下敷きにしているようだ。小説では、曲中にも出てくるSeverinという男が重要な役割を果たすらしい。
僕はこの小説を読んでいないため、この曲の立ち入った批評はやめにする。ただ、ストリングスの音がなんとも耳触りでエロく、ただならぬ気配を感じさせる曲であることは確かだ。
いつかは元ネタの小説を読んでみようと思う。
#5"Run Run Run"。何度も繰り返される「走れ、走れ、走れ」というメッセージこそ機械じみてはいるが、その合間に挿入されるカオティックなギターの音が、機械の軋みを思わせる。
間奏のギターソロの早弾きには規則性などみじんもなく、ただ弦をかき鳴らす乱暴さが際立つ。
You gotta run, run, run, run, run Take a drag or two
問題はこの drag という単語である。これは「ドラッグ、薬物」を意味する drug ではない。音的にも、このアルバムのテーマ的にも、非常に間違えやすいので注意していただきたい。
take a drag は「煙草を吸う」という意味である。したがって、"Take a drag or two"は「一本か二本吸っていきなよ」という意味だ。
ドラッグは確かに The Velvet Underground が何度も扱うテーマではあるが、この曲に限っては、それとは関係ないのではないだろうか。
#6"All Tomorrow's Parties"では、再び Nico がメインボーカルへ。タンバリンの音も健在である。そしてやはり、機械を感じさせる整然とした音楽。
ボーカルにエフェクトをかけ、「繰り返して」聴こえるようにする(2番の歌い出しとか)あたりもおそらく意図的にやっているのだろう。
"what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties?"(明日のパーティーに、貧乏な女の子は何を着ていけばいいの?)という歌詞は、#4"Venus In Furs"に出てくる "chase the costumes she shall wear"という歌詞と酷似している。もしかすると、"All Tomorrow's Parties"に出てくる主人公の女の子は、"Venus In Furs"でSeverinを凌辱しているVenusなのかもしれない…?
さて、#7"Heroin"はこのアルバムの中心となる曲ではないだろうか。
なぜなら、この曲は「人間と機械との決定的な違い」を表現しているからだ。
The Velvet Underground - Heroin - YouTube
機械は、ヘロインを摂取しない。酩酊状態にもならない。心を持たない。
反復されるメロディ、歌詞、ギターストローク、ドラムス…。Warhol がそれらに託した「機械」というメッセージに対して、The Velvet Underground はヘロインという猛毒を仕込む。
機械には、決して効かない毒を。
縦横無尽に空間を切り裂くギターソロと、それこそ千鳥足のように変わるテンポを味わって、僕たちは思わず身体を揺らしてしまう。頭を振ってしまう。まさに、前後不覚によっぱらってしまった人間のように。
"Heroin"に使われているコードは、IとIVのたった2つだ。コンピュータは0と1の2進法で動く。その意味で言えば、2つのコードしか使わないこの曲も2進法で動く「機械」を意図しているのかもしれない。しかし、トニックコードのIとサブドミナントコードのIVの反復から僕たちが感じるのは、心地良い弛緩と緊張の連続である。そして、そのコードの繰り返しは次第に中毒性を帯びてくる。
そんなふうにこの毒を味わえることこそ、僕らが決して機械ではないということを、証明しているのではないだろうか。
「ヘロイン、わが妻、わが人生」と Lou Reed は歌う。もちろん僕は薬物を摂取したことはないが、ヘロインを人の心を狂わせる音楽という毒だと考えるのであれば、大いに賛成である。NO MUSIC, NO LIFE.
#8"There She Goes Again"、#9"I'll Be Your Mirror"は、どちらも短くこれといって印象にも残らない曲である。といってもどちらも良い曲だし、アルバムを聴く時に飛ばしたりはしないのだが。これまでで述べてきたように、#8は最後にテンポが変化するあたりが「人間」、#9は Nico のボーカルとタンバリンを中心に据えた「機械」である。
#10"The Black Angel's Death Song"もその前2つの曲と同じく短いが、ニュースを朗読しているかのようなボーカル、時折挟まれる蒸気のような音が特徴的だ。かなり即興的な要素を取り入れられていて、この次の曲でありアルバムのラストを飾る曲#11"European Son"を予感させる。
「即興的な音楽」といって思い出すのは、もちろん彼らの代表曲の1つ"Sister Ray"。そして"European Son"も、非常に即興的な曲である。(英語版Wikipediaには、"European Son"が"Sister Ray"の原型であると書かれている。)
特に"European Son"は、空間に隙間がほとんどない曲だ。「隙間がない」とはどういうことかというと、聴いていてテンポや音の空白を感じない、ということである。
空間を音で埋め尽くす隙間のない音楽としてよく取り上げられるのは、My Bloody Valentine を代表とするシューゲイザーである。The Velvet Underground のやっていることはシューゲイザーではないが(そもそも時代的に全然違う)、非常にノイジーで空間的に隙間のあまりない音楽をやっていることに変わりはない。そして、隙間のない音楽ではあるが、非常に「軽さ」を感じる音楽でもある。
このあたりが、Warhol が開発した「ブロッテド・ライン」という絵画的手法との共通点である。ブロッテド・ラインとは、描いた絵にインクを乗せたところに別の紙を押し付けて転写する手法であり、彼の代表的な作品にももちろん使われている。
僕が「アンディ・ウォーホル 永遠の15分間」で彼の作品を鑑賞して感じたのは、「塗りつぶしにも関わらず軽さを感じさせる」ということ。それは、僕が 'The Velvet Underground & Nico' の音楽性に感じる「隙間はないけれど、軽い」という印象と、ほぼ同一である。
表現手段には絵画と音楽という違いはあっても、Warhol の表現したかった「雰囲気」や「感じ」といったものは、おそらく同じである。
意識しようとしまいと、人の個性というのは、その人が表現したものに必ず現れる。機械ではこうはいかない。ランダムに変数を発生させ、「個性」などまるで感じさせない振る舞をすることも、簡単にできる。
絵画や音楽から感じられる Warhol の「彼らしさ」こそ、彼が機械ではなく人間だったということを、示しているのではないだろうか。
ロックの歴史上、大変に重要な作品とされている 'The Velvet Underground & Nico'。しかし、これは単なる歴史上の名作にはとどまらない。そのポップネス、中毒性、そしてメッセージ…。どれをとっても、素晴らしいとしか言いようのないアルバムである。
50年も前の作品なんて古臭い、などと思わず、一度聴いてみてはいかがだろうか。
あなたも、機械と人間のせめぎ合いを感じ、最後には自分が人間であることに喜びを覚えるはずだ。
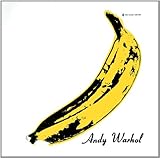
Velvet Underground & Nico-45th Anniversary
- アーティスト: Velvet Underground
- 出版社/メーカー: Polydor / Umgd
- 発売日: 2012/10/25
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
関連記事:
'White Light/White Heat' - The Velvet Underground / きみは、この白い熱を感じるか。ロック史に残る傑作。